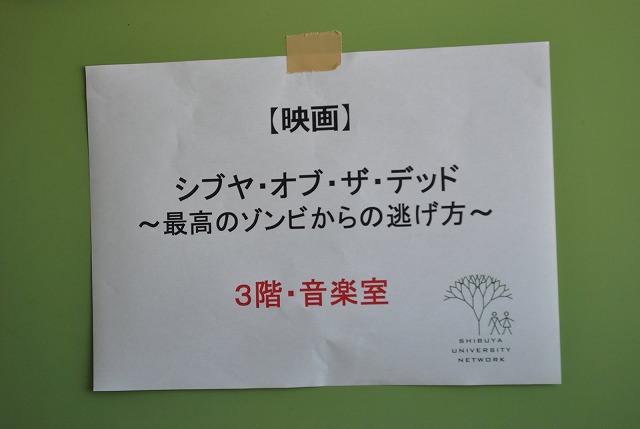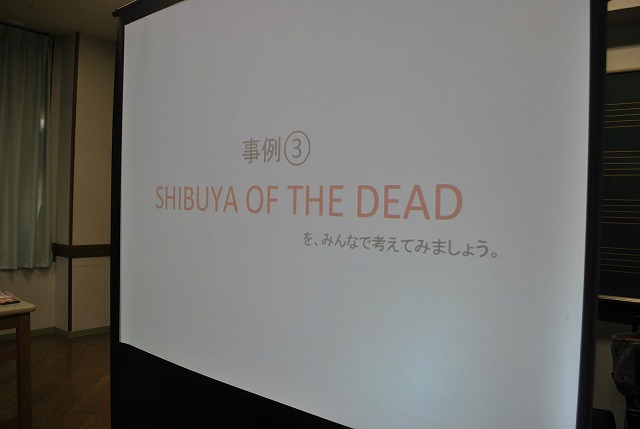授業レポート
2014/10/18 UP
シブヤ・オブ・ザ・デッド
~最高のゾンビからの逃げ方~
今回の授業は、ゾンビを”こよなく愛する”映画監督の山本清史さんが先生です。
ここで言う”こよなく愛する”とは、山本監督がゾンビをテーマにした映像作品を数多く発表していらっしゃるからだけではありません。なんと監督は日常的に「もしここで、ゾンビに襲われそうになったらどうするか?」「誰かがいきなりゾンビになったら、どう対処するか?」を考えてしまうそうです・・・頭の中はゾンビでいっぱい!?
そんな山本監督とゾンビの魅力をたっぷり味わう2時間半でした。
まずはご自身の監督作品「EDO OF THE DEAD」を鑑賞。
舞台は江戸時代。死人(≒ゾンビ)が次々と蘇り、人々を襲うことで、この世で生きる人たちの「生と死」の境が曖昧になっていきます。「生きるとは一体何か?」という普遍的な問いを投げかけるストーリー。
山本監督はこの映画を通じて、ゾンビが人を襲う時のアクションや演出の追求、
人がゾンビを殺す意味、このような状況下でなんとか生き抜く人々を描きたかったそうです。
なぜゾンビ×時代劇なのでしょうか?
時代劇を選んだ動機を山本監督はこう語りました。「時代劇は、日本が世界に誇れるコンテンツ。ハリウッドでもたくさん侍映画が作られているけれども、やはり日本人が作った方がいいと思う。現代では製作者も視聴者も、あまり時代劇に良いイメージを持っていないが、歴史的事実をいかに娯楽として楽しめるものにするか、そこに挑戦したかった。」。
続けてゾンビにフォーカスした理由は下記の4つだそうです。
1. 歴史的事実とのマッチングが良い
⇒江戸時代の風習や時代背景が、ゾンビの存在を違和感のないものにしていること
2. ビジネス規模が大きい
⇒すでにゾンビをモチーフにして、ヒットしているコンテンツが多数あること
3. 他のモンスターよりも製作の敷居が低い
⇒基本的に「メイクして、汚して、歩かせる」だけで、誰もがゾンビになれること
4. ゾンビ映画はジャンルを選ばず拡張性がある
⇒コメディ映画からシリアスなものまで、幅広く取り扱えること
さらにゾンビは、文明批判や死生観、人間とは一体何か等の壮大なテーマと非常に相性が良く、見る人々に「死と隣合わせの状態での意思決定」を考えてもらうことができると話されました。ここからも、山本監督が“ただゾンビが好きだから、映画にしよう“という理由で、作品を作るわけでは決してないことがわかります。監督自身が無類のゾンビ好きだからこそ、「なぜゾンビを扱うべきなのか」ということを、常に考えていらっしゃるというのがひしひしと伝わってきました。
参加者の皆さんも、山本監督の熱い話にどんどん引き込まれました。
授業の後半は、参加者同士でグループワーク「シブヤ・オブ・ザ・デッド」を行いました。お題は「もしも渋谷のスクランブル交差点に、ゾンビが現れたらどうするか?」です。そもそも逃げるのか?戦うのか?逃げる方法は?戦う場合の武器は?などなど多くの疑問がアタマの中を駆け巡ります。
「公共の交通網は麻痺するだろうから、ドン・キホーテで自転車を買って逃げる」
「NHKに乗り込んで、国際放送で助けを求める」
「地下に隠れ夜になるまで待ち、その後渋谷から脱出する」
自分事として考えることで、生徒さんたちの口からはリアリティのある回答が続出します。
中でも一番多かったのは、「東急ハンズで武器を調達し、身を守る(戦う)」という意見。皆さん東急ハンズなら何かしらあるというイメージを強く持っているのですね。
授業の最後は「EDO OF THE DEAD」でメイクをご担当された征矢杏子さんのレクチャーで、2人1組となりゾンビメイクを体験しました。ハロウィンが近いので、気分はうきうきです。
メイクのポイントは、血色を悪く見せることと顔を痩けさせること。スポンジや綿棒を駆使して、何度も色を重ねてリアルなゾンビ顔に近づけていきました。
結果的には、個性豊かなゾンビ顔が大集合!山本監督を囲み、全員で記念撮影をして授業を終えました。
【わたしのまなび】
私自身は、ホラー映画やスプラッター映画が、大の苦手です。ゾンビなんて、もっての外です。これまでの人生において、ゾンビ映画を見たことはありませんでした。
今回が初めてのゾンビ映画の鑑賞となったわけですが、正直、目を覆いたくなる瞬間やびくっとするシーンが何度もありました。見慣れている人ならどうってことのないシーンでも、ダメな人には、ダメですね・・・
でも、山本監督のお話から、ゾンビは怖いけれども、その湧き上がる恐怖心によって、「生きる意味」や「生死をさまよった時に、何を考えるのか」といったメッセージが観客に届くのだと感じ、ゾンビの奥深さを味わえた時間でした。
【レポート:ボランティアスタッフ 岩崎恵美】
【写真:ボランティアスタッフ 大竹悠介】