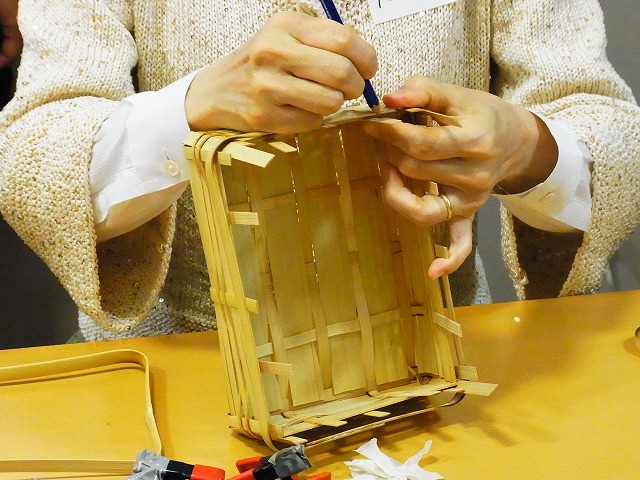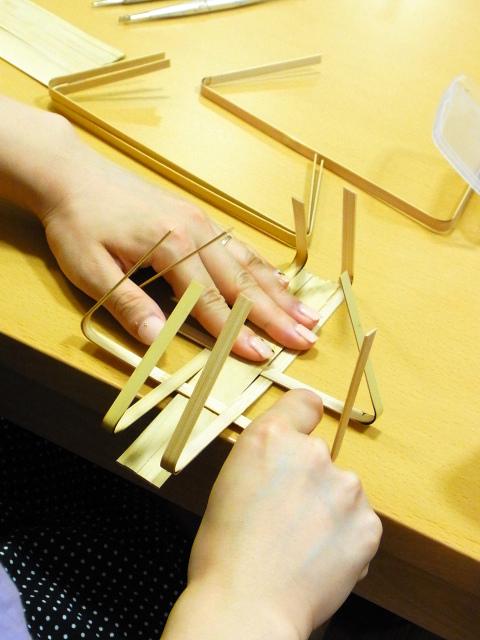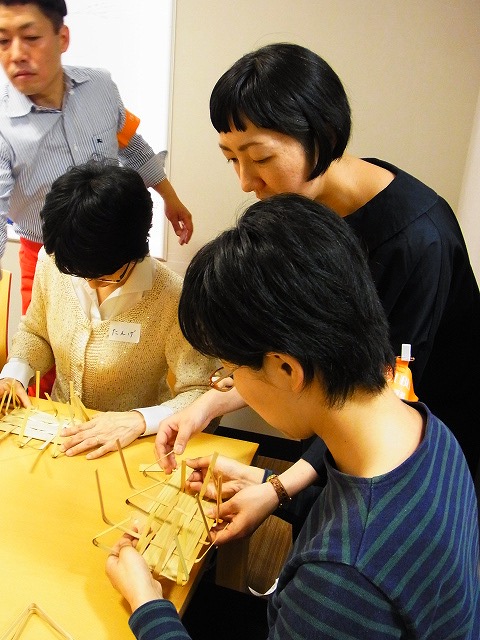授業レポート
2012/5/22 UP
みんなの図工室14 ~伝統の技に学ぶ 竹の角物トレーづくり~
「今日は一番楽しいところをやってもらいます♪」
今日の先生は、角物作家ユニットの小代夫妻。
大分の工房を拠点にしつつも、展示会やワークショップで全国を回ってらっしゃいます。
「いま準備しているこの状態で、もう8割終わっているんです。
竹の伐採から、実際に竹を組む作業にいたる前までの作業が一番大変なんですよー。」
竹の職人さんと聞けば、もうずーっと竹を組んでるイメージがありました。
でも実は、組むまでの作業もほとんどご自身でされているとのこと。
山に生えている竹を切り、油を抜き、切りそろえ、組みやすい薄さに揃える。
さらに、熱を加えて曲げて形を整える作業を終え、やっと最後の組む作業にとりかかることができます。
今日は、その“最後の一番楽しい”部分を体験させていただきます。
そんな大変話をしつつも「僕は口も動くけど、手も動くよー!」
とおっしゃるとおり、リズム良く竹を操る先生。
あっという間に、準備完了。
さぁ、授業開始です。
今回作る「角物」とは、先生曰く
「竹のパーツを組み合わせてつくるプラモデルのようなもの」
「編む」のではなく、「組む」
確かに準備された材料は、いくつものパーツに分かれていて
どれがどこに使われるのか素人では???な状態です。
本当に出来るのかちょっと不安になりますが、
先生のお手本をじっくり見ながら、慎重にパーツを組み始めました。
お話好きの先生と世間話に花が咲きつつも
さすがに図工好きのみなさん、どんどん組み上がっていきます。
今回は女性のみ参加でしたが、工程を見ていると
意外に男性もハマりそうな作業だなぁ、と思います。
一度、こういったワークショップに参加されて、
次はパーツを譲って欲しいと問い合わせがくることもあるそうで
楽しそうに組み上げていく皆さんを見ていると納得です。
最後に側面の縁の部分をきれいに処理すれば、
竹かごトレーの出来上がり。

明治時代から使われていた角物は
豆腐の水切りかごなど、少し昔ならどこの家庭にもあった暮らしの道具。
今は、職人さんがほとんどいないのでなかなか手に入りずらいですが、
先生のおかげで身近に感じることができました。
先生のお二人ありがとうございました!
(シブヤ大学事務局スタッフ:増沢有里 )
今日の先生は、角物作家ユニットの小代夫妻。
大分の工房を拠点にしつつも、展示会やワークショップで全国を回ってらっしゃいます。
「いま準備しているこの状態で、もう8割終わっているんです。
竹の伐採から、実際に竹を組む作業にいたる前までの作業が一番大変なんですよー。」
竹の職人さんと聞けば、もうずーっと竹を組んでるイメージがありました。
でも実は、組むまでの作業もほとんどご自身でされているとのこと。
山に生えている竹を切り、油を抜き、切りそろえ、組みやすい薄さに揃える。
さらに、熱を加えて曲げて形を整える作業を終え、やっと最後の組む作業にとりかかることができます。
今日は、その“最後の一番楽しい”部分を体験させていただきます。
そんな大変話をしつつも「僕は口も動くけど、手も動くよー!」
とおっしゃるとおり、リズム良く竹を操る先生。
あっという間に、準備完了。
さぁ、授業開始です。
今回作る「角物」とは、先生曰く
「竹のパーツを組み合わせてつくるプラモデルのようなもの」
「編む」のではなく、「組む」
確かに準備された材料は、いくつものパーツに分かれていて
どれがどこに使われるのか素人では???な状態です。
本当に出来るのかちょっと不安になりますが、
先生のお手本をじっくり見ながら、慎重にパーツを組み始めました。
お話好きの先生と世間話に花が咲きつつも
さすがに図工好きのみなさん、どんどん組み上がっていきます。
今回は女性のみ参加でしたが、工程を見ていると
意外に男性もハマりそうな作業だなぁ、と思います。
一度、こういったワークショップに参加されて、
次はパーツを譲って欲しいと問い合わせがくることもあるそうで
楽しそうに組み上げていく皆さんを見ていると納得です。
最後に側面の縁の部分をきれいに処理すれば、
竹かごトレーの出来上がり。

明治時代から使われていた角物は
豆腐の水切りかごなど、少し昔ならどこの家庭にもあった暮らしの道具。
今は、職人さんがほとんどいないのでなかなか手に入りずらいですが、
先生のおかげで身近に感じることができました。
先生のお二人ありがとうございました!
(シブヤ大学事務局スタッフ:増沢有里 )