
ソーシャルファーム(Social Firm)という存在をご存知ですか?
誰もが楽しく働くことができるような職場。挫折があっても、失敗があっても、困難があっても、障害があっても、働きたいと思っている人は多い。そうした人々が働くことができる場所が「ソーシャルファーム」です。
でも、ソーシャルファームは特別な場所じゃないんです。どんな会社でもソーシャルファームになることができる。
このワークショップは、ソーシャルファームとはどういうものか、どんな会社が取り組んでいるのか、どんな人がどんなふうに働いているのか、どうやってソーシャルファームになれるのか、さまざまな人々が楽しく働くことができるソーシャルファームの思想と実践を知り、未来の社会を考え、作る場所です。
2024年 第2回テーマ「さまざまなソーシャルファーム」
2024年10月16日(水)19:00〜21:00

ソーシャルファームというのは、障害や病気や引きこもりなど、さまざまな理由から働きたくても困難を抱えている方々と他の従業員とが一緒に働きながら、自立的な経営が行われている社会的な企業のことを指しています。2024年第2回は、東京都のソーシャルファーム認証を受けている企業から、フラワー事業を営む株式会社ローランズ代表取締役の福寿満希さんと、昨年もご協力いただいたIT企業のディースタンダード株式会社代表取締役の小関智宏さんという業種の異なる2つの会社にお越しいただきました。

お二人の会社は、お花とITというまったく異なる世界ですが、共通していたのは、働きたくても働けていない人がいるのであれば、その人に仕事を合わせよう、という思い。学生時代に特別支援学校の教員免許を取得した福寿さんは、「そこで出会った子どもたちが抱いている“お花屋さんになりたい”“ケーキ屋さんになりたい”という夢を実現できる世の中でありたい」という思いを抱き、11年前にフラワーショップを開業。現在、全社80名ほどのスタッフのうち、55名が障害などを抱えたスタッフがおり、フラワーギフトや空間緑化、就労移行支援(フラワーアカデミー)などを展開。働く時間やできることに制限のある人でもできるような分業体制や短時間就業を導入しています。

一方のディースタンダード社は、若者が輝ける職場を、と引きこもりや自閉症、出所者などの方々がIT技術者の資格を取得するために、社内でスモールステップを積み上げながら勉強できるプロセスをつくったり、社員同士の交流機会を頻繁に設けていたりしています。
いずれも障害や病気、あるいは引きこもりや出所者であるという背景を持っていたとしても、働き方のスタイルを変えたり、担当業務を変えたり、出勤が難しいならその人の働き方に合わせる、できることを増やしていく……などを会社の方針としてサポートしているといえます。
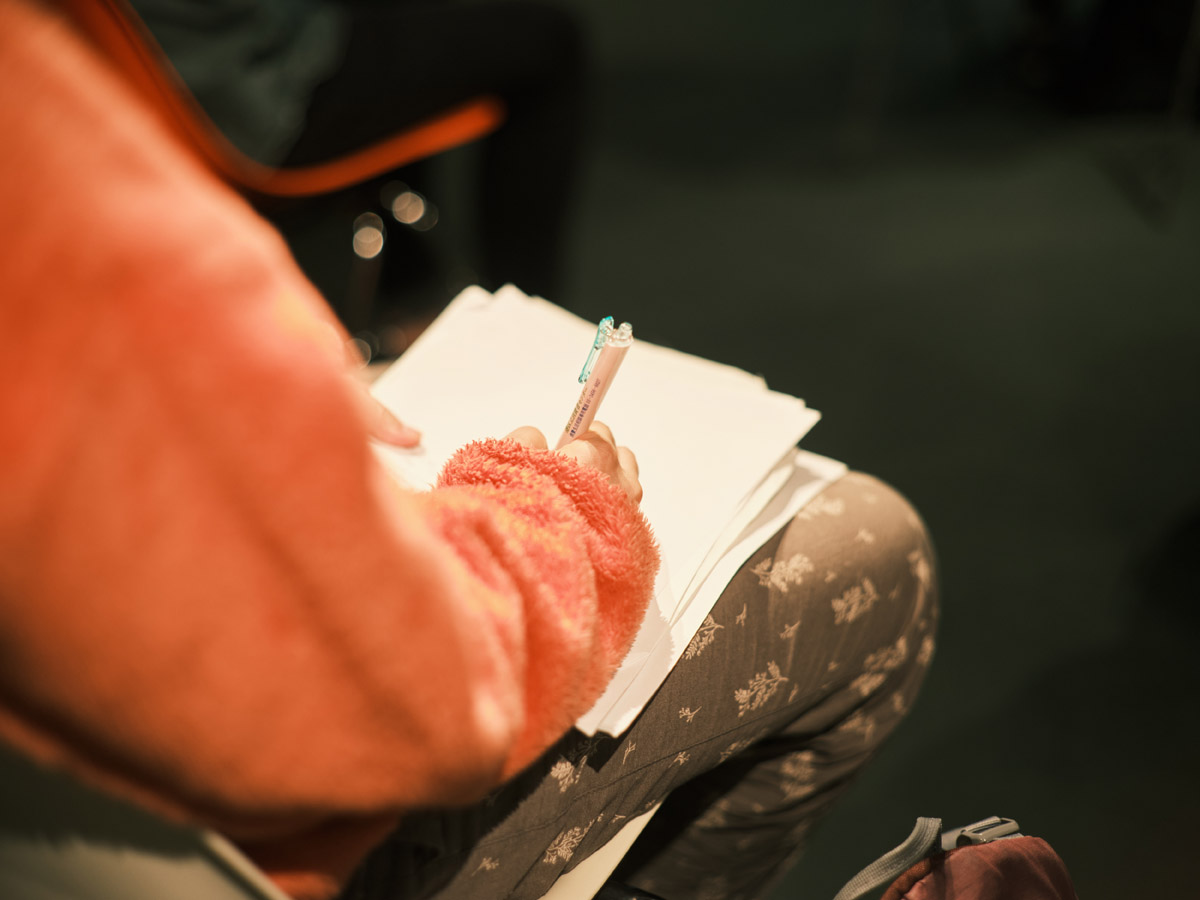
そして現在、ソーシャルファームの枠組みではないけれども、就職氷河期の人たちにも門戸を開いています。「同業他社はこの層の人たちを戦力化させていないんですよ。我々はいまこれを頑張っています」と小関さん。お二人の会社経営の姿勢は、会場にも大きな刺激と共感を呼び起こしたようです。
また、東京都のソーシャルファーム認証としては、全従業員の20%以上が就労に困難を抱えている人である必要があります。お二人の会社は、認証される以前からそうした人々を積極的に雇用していた企業ですが、ソーシャルファームという認証ができたからには、今後、認証団体の交流の機会、個別事情の相談と解決に向けた支援などについてはまだ課題があるのでは、と小関さんより指摘がありました。

お二人の発表の後、会場からは積極的な質問が相次ぎ、また、グループに別れてのディスカッションも熱を帯びた様子。グループワークの発表を受けて、近藤先生からは、「今日はいろんなキーワードがありました。
経営者が経営していく上でいちばん大事なのは、その人の人生における目的だったり問題意識だったりを、会社という形でどう体現していくかというところだと感じました。お二人はそれを経営者として体現してこられたわけなんですけど、それがソーシャルファームの経営に行きついている。ソーシャルファームという形で一体何をやろうとしているのか、それが経営とどういう接点があったのかというと、いわゆる就労困難者と言われる人たちに心を寄せて、そうした人たちを歓迎しているということ、歓迎するための方法論として経営を使っているということだと思います。それを今日見せていただきました。

6つのグループのみなさんのコメントにもそれがありました。歓迎していること、迎え入れていること、そこに向けて何ができるかを考えること……不安が晴れたということとか、そういう会社があるんだと知ったということとか、多様な人たちを受け入れるということで、結果、社会の幅が広がっていくんじゃないかということだったり。それが経営者としての成功にも会社の運営の成功にもつながる。その結果、会社としてこういう考え方を持つことが広がっていくんじゃないかというポジティブな側面を見てくださった方たちがたくさんおられたと思います。次回3回・4回目と、さらにそのリアルを追求していくような話が進んでいきますので、この後もまた議論ができればと思います」。
最後に、小関さんから、こんな言葉をいただきました。「残念ながら合わなくて辞めることになった……という時に、『ソーシャルファームの仲間たちがいて、あそこに行ってくれれば大丈夫です』と言いたい。ソーシャルファームの企業同士でバトンを渡せるように、ちゃんと次の行き場所があって、安心してどこでも行けるよ、っていうのを目指したいなって思ってるんですよ」。
ソーシャルファームの議論は、どこでも安心して働きたい人たちを受け入れられる社会をつくる話だと改めて強く感じます。そしてまた、会社を支えてくれる人たちもいる、困難な人たちを支えてくれる人たちもいる……そういうさまざまな層があり、その厚みがある社会になっていく未来を始めなくては、と感じたのでした。