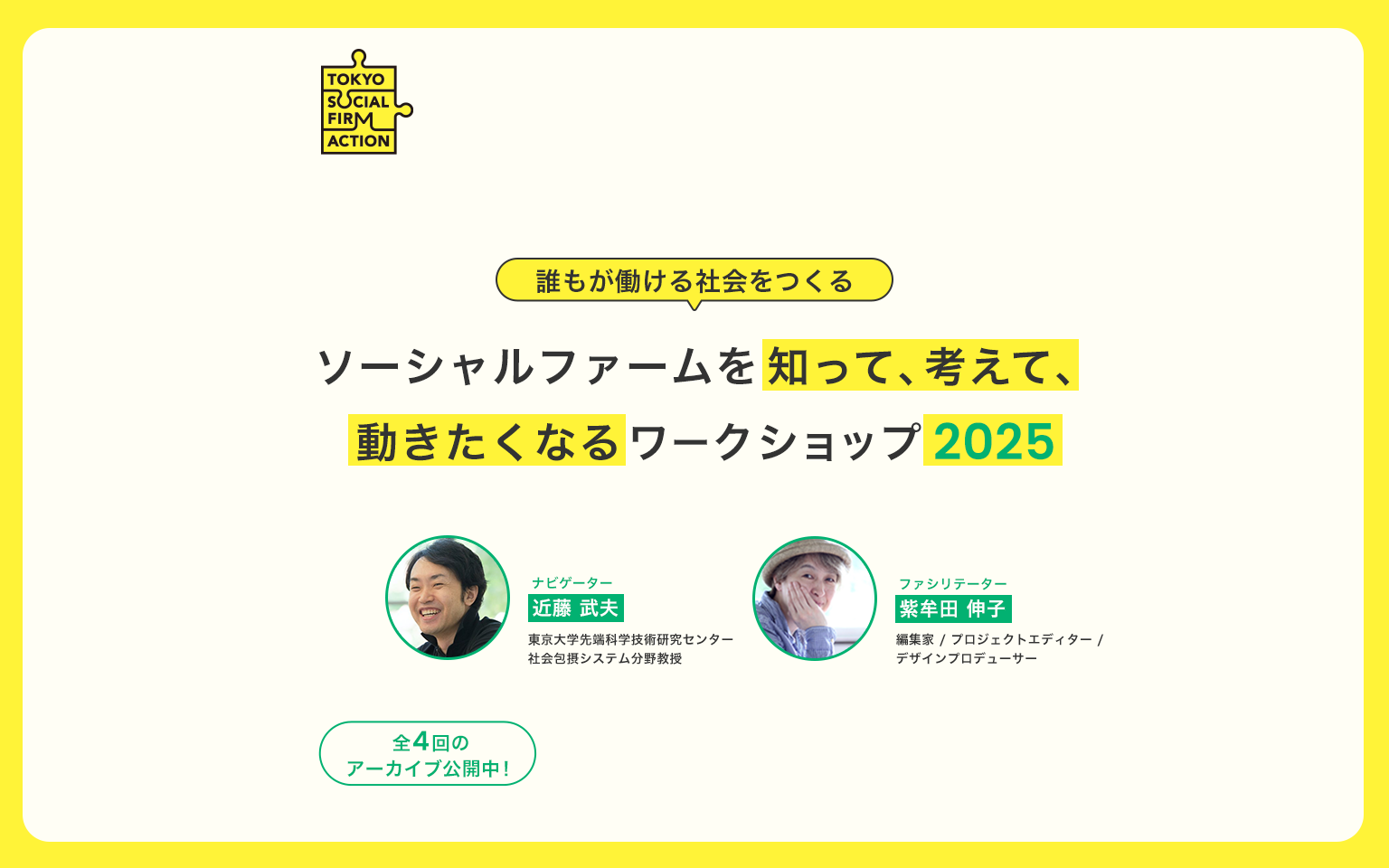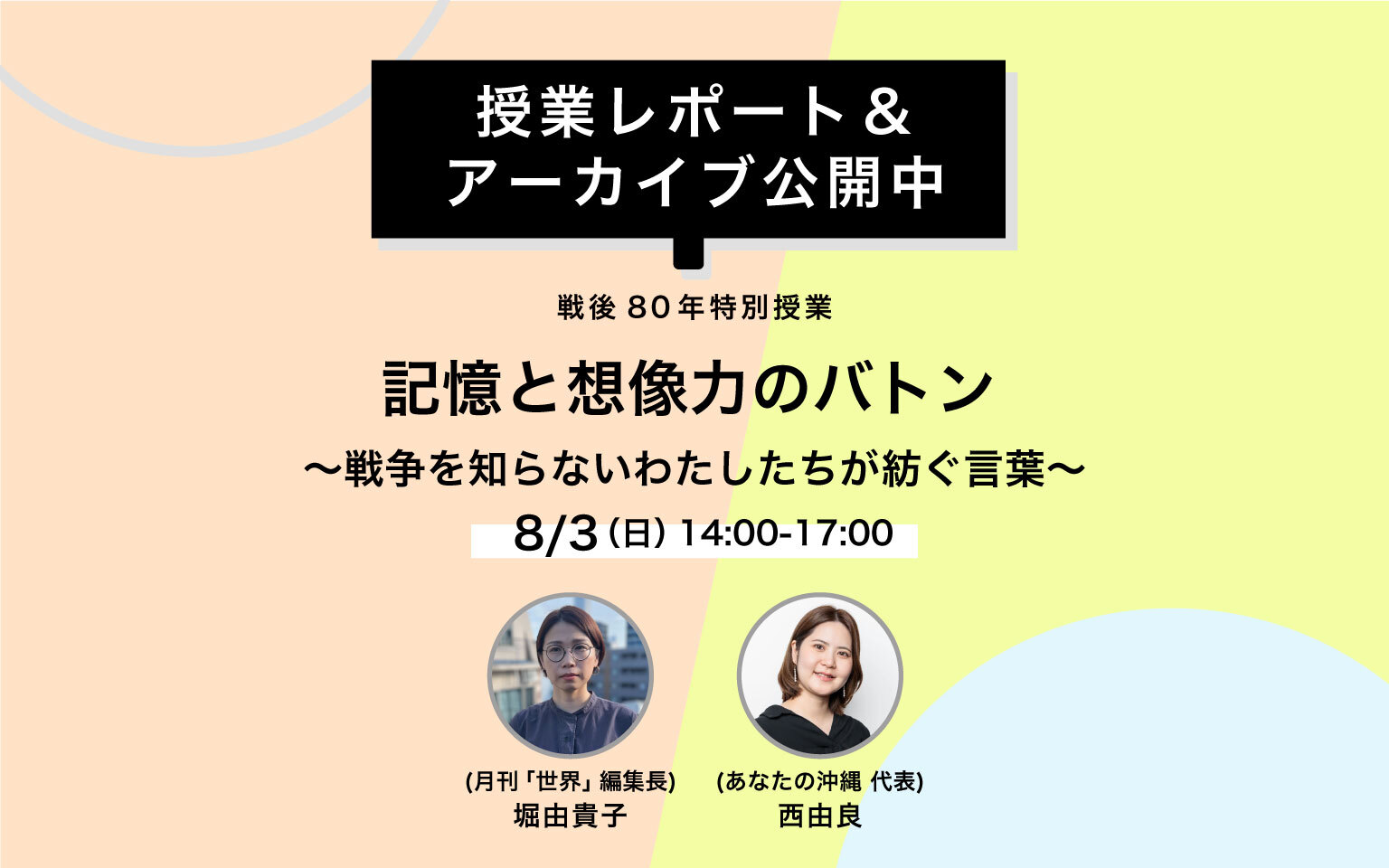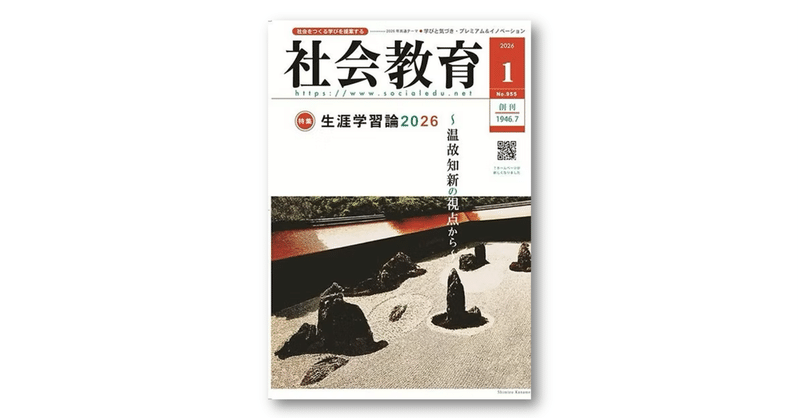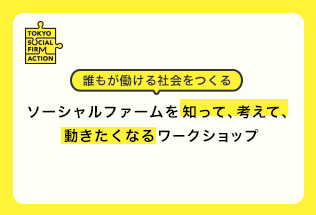シブヤ大学は、
“見つける学び場”です。
シブヤ大学は、まちのあらゆる場所を教室に、多様な授業を開催しているNPO法人です。
2006年の開校以来、開催した授業は1,600講座以上。これまでに45,000人以上が参加しています。
新着授業
誰でも参加できます!
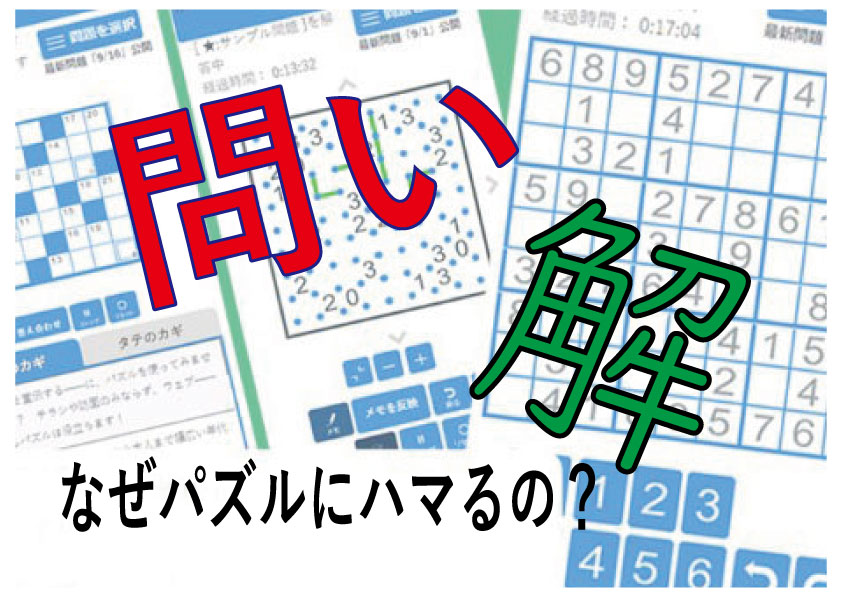
「問い」と「解」について考える
~なぜパズルにハマるのでしょう?~

ペルーの手仕事と森の恵の魅力を深掘り!元JICA隊員たちとの南米カルチャートーク!

「今夜は、無礼講。2026」~お座敷あそびは奥が深い!
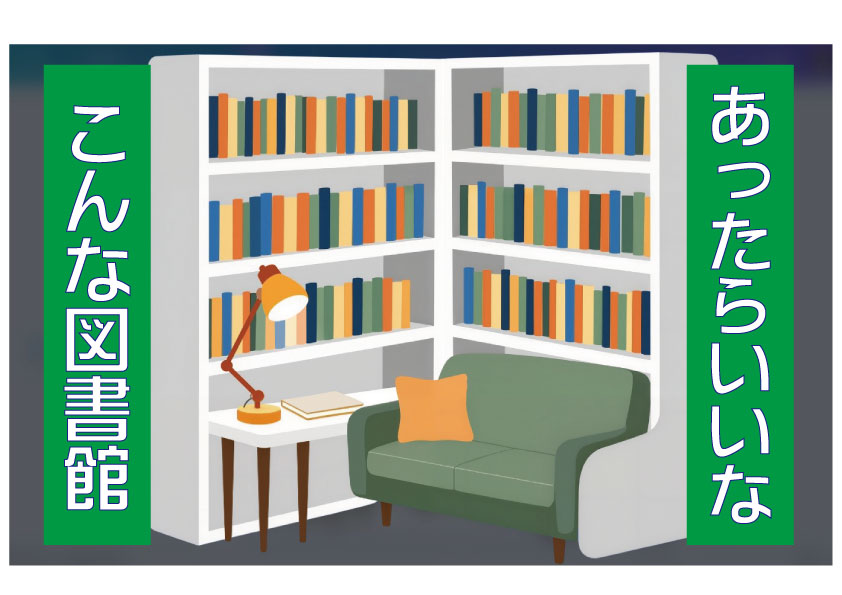
あったらいいな、こんな図書館
~図書館の新しい使い方を考える~

マイ・リトル・ブッダをつくろう〜恋愛編〜
.jpg)
【トライアルツアー / Trial Tour】見えない川をたどる、渋谷の物語 / Trace Shibuya’s Stories Along a Hidden River
最新授業レポート
終了した授業の内容をお伝えします

ひとりの大人として、誰かの“安心”になれる 〜バディチームが目指す「みんなで子育て」とは〜
本授業は、前半にNPO法人バディチーム理事長の岡田さんによる講義、後半に講義を受けた参加者が二つのグループに分かれ、印象に残った点や感じたことを中心に対話を行うセッション、という二部構成で進められました。「さまざまな理由で子育てが大変になっている家庭に訪問して子育て支援を行い、虐待防止などに取り組む」というテーマは、社会的に重要である一方で非常に重く、どのような授業や対話になるのだろうか、授業前は少し期待と不安が混じっていました。私自身が今回、スタッフとしてこの授業に参加した理由は、子ども虐待などの事件のニュースに触れるたびに、強いやりきれなさや無力感を覚えながらも、当事者への支援というところまで自分が踏み込めていない現状があったからです。問題意識は持っているものの、実際にどのような支援が行われているのか、支援に携わる人たちがどのような思いで活動しているのかを知らないままでは、自分の気持ちもどこか宙に浮いたままのように感じていました。今回の授業は、そうした疑問に向き合うきっかけになるのではないかと考え、参加を決めました。岡田さんの講義では、訪問型子育て支援を行う「バディチーム」の具体的な活動内容について、丁寧な説明がありました。支援の対象となる家庭の状況や、その背景にある社会的な要因、また、支援を進める際に大切にしている考え方についても、具体例を交えながら語られていました。支援を必要とする家庭から本当に声が上がるのか、声が上がらない場合にどのように家庭を見つけ、どのようにアクセスしていくのか、講演や後半の対話セッションにおける参加者からの質問に対しても、一つひとつ誠実に答えてくださっていたことが印象的でした。このようなやり取りを通して、これまで断片的な情報としてしか知らなかった「訪問型子育て支援」という取り組みについて、その全体像を少し理解できたように感じています。特に印象に残ったのは、支援において使われる言葉の選び方です。家庭の状況を「問題」と表現するのではなく、「心配」という言葉に置き換えて関わっているというお話がありました。「問題」という言葉には、どうしても評価や断定のニュアンスが含まれがちですが、「心配」という言葉にすることで、「一緒に向き合いたい」「同じ立場で考えたい」という姿勢が相手にも伝わりやすくなるという説明に、深く納得しました。言葉一つで関係性のあり方が大きく変わること、そしてその言葉選びが支援の入口として非常に重要であることを改めて実感しました。また、団体名に「バディ」という言葉が入っている通り、支援する側とされる側という上下関係ではなく、相手に寄り添い、同じ目線で、同じ方向を向いて課題に取り組む姿勢が一貫していることも強く伝わってきました。支援を行う際に、「してあげる」という印象を相手に持たれないよう、関係性を丁寧に築きながら活動を続けてきたというお話からは、家庭ごとに事情が異なる中で、一つひとつの関係に向き合うことの難しさや、時間と労力を要する現場の苦労がうかがえました。さらに、バディチームの活動が単独で行われているのではなく、他のNPO団体や行政、学校などと、それぞれの役割に応じて連携しながら進められている点についても学ぶことができました。特に、子ども家庭庁の設立をきっかけに、子どもや家庭を取り巻く支援がより組織的につながり始めているというお話は印象的でした。個々の善意や努力に頼るのではなく、社会全体で子どもと家庭を支える仕組みが少しずつ整えられてきていることを知り、希望を感じると同時に、その仕組みを実際に機能させていく難しさについても考えさせられました。一方で、活動内容を多くの人に理解してもらうことの難しさについての話もありました。具体的な事例を紹介することは理解を広げるうえで重要ですが、同時にプライバシーへの最大限の配慮が求められます。そのために、事例をある程度抽象化し、マンガという形で表現する工夫がなされているという紹介がありました。支援の現場を伝えたいという思いと、当事者を守る責任との間で、常に悩みながら発信を続けていることが伝わってきました。後半の対話セッションでは、参加者同士がそれぞれの立場から感じたことや考えたことを共有しました。「普通」という言葉の難しさや、自分自身が育ってきた家庭環境を基準に物事を判断してしまう危うさ、不適切な養育環境が世代を超えて連鎖してしまう可能性など、簡単には答えの出ないテーマについても率直に意見が交わされました。参加者の多くが強い問題意識を持ち、「何とか力になりたい」という思いを抱いていることが伝わってきたことも印象的でした。一方、講義資料の中で示された「児童相談所における児童虐待相談対応件数」のグラフでは、1990年には1,101件だった相談件数が、2001年には23,700件、そして2023年度には225,509件にまで増加しているという数字は、想像をはるかに超えるものでした。この増加は、子どもの数が減少している中で虐待そのものが増えているのか、相談という行為が社会に浸透してきた結果なのか、いずれによるものかは単純に結論づけることはできません。しかし、ニュースとして報道される虐待事件が、実際にはごく一部に過ぎないという現実を突きつけられたように感じました。本授業を通して、子育て支援や虐待防止の活動は、特別な誰かが「してあげる」ものではなく、当事者と同じ目線に立ち、関係性を丁寧に築きながら「一緒に向き合う」営みであることを学びました。家庭ごとに異なる状況の中で、画一的な支援が通用しない難しさを感じる一方で、だからこそ人と人との関係性を大切にした支援の持つ力を強く実感しました。今回の授業は、これまで漠然と抱いていた「何かしたいが、何ができるのかわからない」という思いを、現実の活動や具体的な言葉を通して見つめ直す貴重な機会となりました。支援の現場を知ることは、社会の課題を知ると同時に、自分自身の立ち位置を問い直すことでもあると感じています。今後も、この学びを一過性のものにせず、社会の中で自分に何ができるのかを考え続けていきたいと思います。(レポート:山口圭治、写真:小林大祐)

いまさらですが「KY(ケーワイ)」のすすめ ~新聞が空気を読まない理由とは~
みなさんは普段空気を読まずに生活していますか?私はいつもまわりの空気を読んで行動してしまいます。この同調圧力の強い日本で暮らすには、それも処世術かなと。でも、今回の授業はいまさらながら「空気を読まない」ことの勧めです。先生は、「東京新聞はなぜ、空気を読まないのか」の著者である東京新聞元編集局長菅沼堅吾さんです。「新しい戦前」の中で権力を監視する役割を持つ新聞の編集局長として権力と対峙してこられました。みなさんは新聞を読んでますか?という問いかけでは、「前には読んでいたけれど、今はSNSのニュースを読んでます」とか「電子版を見ています」という生徒さんが多く、紙の新聞を読んでいる人は少数派でした。そういえば、電車の中で新聞を広げている姿を見なくなりました。昔は満員電車の中で上手に新聞を畳んで読んでいる人がいたものです。今はみんなスマホとにらめっこですよね。先生から新聞の基礎知識、役割、効能に関する講義となりました。まず、新聞の基礎知識のお話しです。新聞が読まれなくなったと言われていますが、実際にはどうなのか?一般紙では2015年4069万部→2025年2,337万部と大幅に発行部数が減りました。先生によれば、「これを『大変な減り方』とみるか『まだ2,000万部以上読者がいる』とみるかによって違ってくる。新聞は毎日2,000万部以上発行されるわけだから大ベストセラーであり、まだまだ新聞には力がある」ということです。また、減り方も最近ペースが落ちていて、やがては底が見えてくるのではと予想しているとのことです。新聞の使命は何でしょう?新聞の使命は権力を監視し「本当のこと」を伝え、警鐘を鳴らすことにあります。(端的には「権力監視」の4文字です)では、権力監視は何のためなのか?それは、かけがえのない命と暮らしを守るためです。究極的には国に二度と戦争をさせないことです。だから権力側の「空気を読まない」「読んではいけない」のです。これが先生の著書の題名「東京新聞はなぜ、空気を読まないのか」の答えでもあります。権力監視が新聞の使命であるとされるのは、次の2点によるものです。① 先の大戦の反省と教訓です。新聞が満州事変から権力監視を放棄し「大本営発表」を垂れ流し国民を熱狂させることで戦争に加担したこと② 憲法が予定した使命です。最高裁判決(1969年)が事実の報道について、国民の「知る権利」に奉仕するので「表現の自由」(憲法21条)の保証のもとにあると明示したこと新聞には、権力の監視と車の両輪であるもう一つの使命があります。それは、「小さな声」の代弁者であることです。記者がいる場所=ニュースの発信地であり、地方紙のキーワードは地域密着であり、支援ジャーナリズムです。ちなみに記者は全国に2025年4月現在14,758人(女性3,926人)もいるということです。情報が無料で入手できる時代に、新聞は何産業なのか?先生は「幸福産業」だというのが持論だそうです。それは、先生の記者人生最初の記事に答えがあったそうです。初出勤の日、支局長から「街を歩いて何でもいいから記事にしてみろ」という感じの指示を受けました。街をあてもなくさまよい、保育園か幼稚園の園児が河川敷の斜面で段ボールをソリ代わりにして遊んでいる場面にようやく遭遇しました。写真付きの短い記事を書くと、地域版に何とか載ったそうです。こんなつまらない記事しか書けないのだと嘆いていたら、読者からは「家族の記念になった」「家族で祝いたいから写真を分けて」と感謝の電話が何本もあったということです。この経験により新聞が人生の幸福に貢献できることに気づいたそうです。では、新聞の特徴とは何でしょう?新聞は手紙のように毎日毎日選りすぐりの記事を届けています。情報の主食かつ安全な岩場であると言われます。SNSとの大きな違いは、次のように整理できます。① 事実に基づく最終の確認を行う「信頼のメディア」であること② 世の中を総覧できる「寄り道のエリア」であること③「定点観測」を行う「熟慮のメディア」であることまた、新聞の効能とは何でしょう?変革期に生き抜く力、人間力を磨けます。新聞を読むには考えることが必要ですが、動画を見るときは考えなくても済む。毎日読んでいると身につく力としては、読解力、文章力、語彙力、思考力、論理力、共感力、情報力、批判力、雑談力、コミュニケーション能力などがあります。先生の講義後、机ごとにグループセッションを行いました。それぞれ新聞やKYについて話し合いをしました。先生に用意していただいた授業当日1月17日の各新聞朝刊の1面トップ記事を調べました。東京は「公安部元幹部ら賠償負担を」読売は「国に災害医療支援チーム」朝日は「顧客から着服など31億円」毎日は「立公新党「中道改革連合」」日経は「大型工事、縮む受注余力」産経は「日伊、戦略的関係格上げ」というように各新聞はすべて異なった内容を取り上げていました。各新聞がもっとも興味のあることを一面トップ記事に取り上げるわけで各新聞の特性が現れる部分です。異なった視点の新聞が発行されていることに意味があるとも言えます。私は新聞を宅配してもらっています。毎日読んではいますが、興味のある場所だけつまみ食いです。今回の授業では普段あまり考えたことがなかった「新聞の役割」そして「新聞の魅力」を教えていただきました。総覧性のある新聞は世の中の様々なことが載っているので、毎日じっくり時間をとって、新聞を読むことを楽しみたいと思いました。そして何より新聞社の皆さんが日々、緊張感をもって権力監視を行い、権力と対峙していることを知り、自分自身も権力に対しては「空気を読まない」ことを心掛けねばと思いました。先生は、新聞の役割や魅力を発信することを目的に、今後新しく一般社団法人を設立して活動していきたいとおっしゃっていました。紙の新聞が引き続き楽しめるよう私も学んでいきたいと思います。(レポート:江藤俊哉、写真:秋澤佐智代、佐藤隆俊)

誰もが働ける社会をつくる ソーシャルファームを知って、考えて、動きたくなるワークショップ 2025 第4回 関西のソーシャルファーム実践者と話してみよう!
こちらからご覧ください!
キャンパスニュース
お知らせやコラムなど
コラボレーション
企業・自治体などとのコラボレーション事例

シブヤ大学に参加しませんか?
シブヤ大学は誰でも気軽に参加できる学び場です。
興味のある授業を受けてみたり、ボランティアスタッフとして学ぶ場をつくったり、関わり方は人それぞれ。
あなたの参加をお待ちしています!