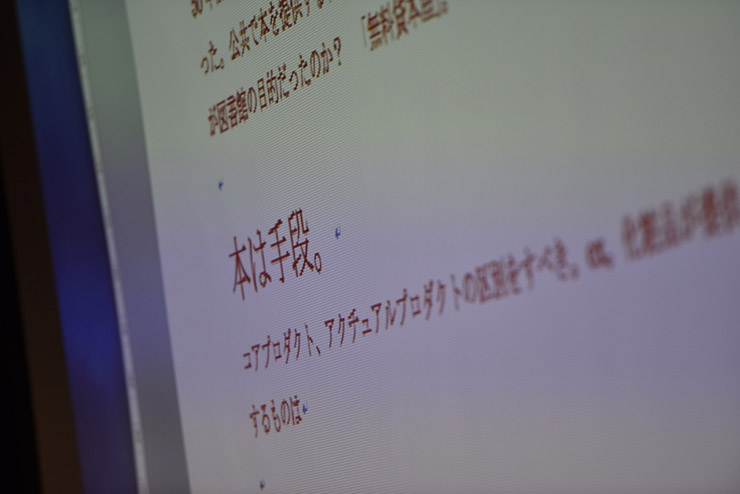児玉史郎
渋谷区社会福祉協議会事務局長
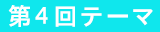
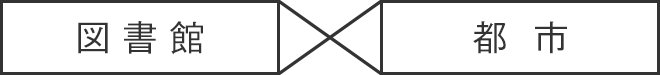
2016年5月11日(水) ヒカリエ8F COURT

渋谷区社会福祉協議会事務局長

東京大学大学院情報学環特任教授・東京文化資源会議事務局長

ファシリテーター
シブヤ大学学長

ファシリテーター
編集家/プロジェクトエディター/デザインプロデューサー
2016年5月11日(水)に開催された都市想像会議(会場:渋谷・ヒカリエ8FCOURT)のテーマは「図書館×都市」。国会図書館におられ、千代田図書館長として公立図書館を改革された柳与志夫さん(東京大学大学院情報学環特任教授・東京文化資源会議事務局長)と、渋谷区の図書館行政に携わってこられた児玉史郎さん(渋谷区社会福祉協議会事務局長)をお迎えして、未来の図書館、とくにこれからの“公共図書館”のあり方について話し合いました。

左:児玉史郎さん、右:柳与志夫さん
行政の公共サービスが転換期にある現在、図書館も例外ではありません。冒頭、児玉さんからは、現状の図書館が抱える、市民のどのようなニーズに応えていくのか、図書資料のあり方や司書という専門職のあり方、そしてそもそも図書館とはどういう場所であったらいいかという問題提起がなされました。
これに対して、「この会場で、今年に入って一度でも公立図書館を使ったことがある人は?」と柳さん。100人近い参加者のうちで、手を挙げたのはなんと6人ほど……。柳さんは、「今日来ている人は図書館に関心がある人だと思いますけれどそれでもこれだけ。それにブックカフェなどを見ても関心はとても高いと思います。それなのに、図書館の現場では利用者が100人にひとりくらいしかコアな利用者がいない。ニーズにそもそも応えていないと思うんですよ」。確かに、ネットで調べ物をしたり、本を売ったり買ったりするのも簡単な時代です。図書館に行くという動機は、多くの人にとって昔とは変わっているのです。
「図書館はなにをどのように提供するかと考えるかで、図書館の意味がまったく違ってくる」と柳さんは言います。図書館として提供しなければならない“コア・プロダクト”は「知」。その知を提供するためのアクチュアル・プロダクトが本なのであって、アクチュアル・プロダクトは状況に応じて変わってくる、と。